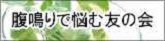| SNS |
|
|
| BBS |
|
|
| CONTENTS |
|
|
| COMUNICATION |
|
|
| サイト内検索 |
|
|
| お勧め |
 
過敏性腸症候群の治し方
|
|
PostBox
(Mail私書箱) |
|
|
|
呑気症候群と腹鳴り
お腹が鳴るとゆうことは胃や腸などの中にある空気が移動することによって引き起こされます。空腹になると脳の命令を受け胃の動きが活性化され胃の中の空気が移動して「ぐぅぅぅ。」とお腹が鳴ってしまいます。また、過敏性腸症候群などによく見られる、腸内ガスの移動によりお腹が鳴る場合もあります。過敏性腸症候群ガス型の場合、腸内でガスが発生することが問題となります。しかしここでは空気を飲み込むとゆう呑気に焦点をあてて腹鳴りを考えてみたいと思います。
唾液を1回のみ込むと、同時に2〜4mlの空気ものみ込みます。炭酸飲料をよく飲む人や早食いの人も、空気を多くのみ込みます。のみ込んだ空気が、のどや食道にたまると、のどの異常感や食道の異物感を感じます。その時、唾液をのみ込んで異物感を解消しようとすると、かえって空気を多くのみ込むことになります。胃に空気がたまると、胃の不快感や痛み、上腹部の膨満感が生じます。胃の空気が逆流して出て来るのがげっぷで、空気が小腸を通過し、大腸にたまるとおならとなって出て来ます。これらの症状が表れる場合を呑気症と呼んでいます。
こうした症状が表れる呑気症は、ストレスの多い人、神経症傾向の人、鬱状態の人がなりやすく、これらの人は、不安や緊張から歯を噛みしめる回数がおおくなり、噛みしめることが発症を促す要因になります。一般に、安静にしているときは、上下の歯は離れています。噛みしめるようになると、舌が上あごに張り付くため、のどの奥に唾液と空気がたまってきて、このたまった唾液をのみ込む際、空気も飲み込んでしまいます。これらのことを噛みしめ呑気症とも呼んでいます。
呑気症の人は、歯をよくかみしめるので、歯をかみ合わせるときに使う筋肉が緊張して、あごやこめかみに痛みが生じ、そして肩や首の痛みや凝り、頭痛、腕のしびれ等の症状が表れることがあります。
ストレスが多くてこの呑気症になる人は、自律神経を介しておこる過敏性大腸症候群を併発しやすく、併発すると、腹部膨満感がより強く表れ、便通異常もみられるようになります。
以下に呑気症への対策法としてはストレスを取り除くこと、食事の仕方の見直し、噛みしめの注意などがあります。
呑気症とストレス、緊張
日常生活をする上で、ストレスは避けて通れません。その人の性格的な問題もありますが、まずは、十分な休息・睡眠をとり、軽い運動、スポーツや趣味を活かしたストレス発散もいいでしょう。そして、物事にたいして100%を望まず、よりリラックスしたプラス思考で生活する事が大切です。
呑気症と食事の仕方
炭酸飲料やビールなど、腸管内でガスを発生しやすいものは出来るだけ避け、早食いをしないように注意し、食事はゆっくりと時間をかけ、よくかんで食べましょう。
呑気症と噛みしめ
噛み合わせが悪いのではなく、噛みしめることが悪いのです。
深呼吸して唇の間から空気を出してそそのまま唇を合わせます。これが顎の筋肉が一番リラックスしている状態(下顎安静位)なのです。舌も上アゴにはついてません。この状態でいるときは飲み込み動作は起こりません。
さらに噛み合わせをしないようにするには薄くて気にならない程度のマウスピース を作ってこれを
歯に被せます。これで噛んだときにマウスピースに気付いて噛みしめを止めるようにするのです。これで歯を合わせる癖を直していきます。 を作ってこれを
歯に被せます。これで噛んだときにマウスピースに気付いて噛みしめを止めるようにするのです。これで歯を合わせる癖を直していきます。
呑気症と後鼻漏
後鼻漏とは鼻水が鼻からのどの落ちてくる病気です。鼻の状態が悪いときは常にのどに違和感があり、それにより頻繁に呑気が起きることがあります。耳鼻科医での治療が必要です。
たけしの本当は怖い家庭の医学(2006/8/1)
に呑気症が取り上げられていました。
以下抜粋
『本当は怖いゲップ〜地獄の迷路〜』
一人息子が小学校に入学したのを機に、マイホームローン返済のため、結婚前に勤めていた会社に再就職したI・Kさん。責任感が強く、よく気がつく彼女は、職場にもすぐ馴染み、何かと頼りにされますが、ある夜、何も口にしていないのに、何故かゲップが出るようになります。その日以来、幾度となく奇妙なゲップに悩まされるようになった彼女。それだけではなく、さらなる異変が続きました。
症状
(1)ゲップ
(2)お腹の張り
(3)おならがしたくなる
(4)おならが臭わない
(5)食欲不振
(6)胸の重苦しい痛み
(7)頭痛
「噛みしめ呑気症候群」とは、緊張やストレスによって体に様々な異変が引き起こされる心身症のひとつ。最悪の場合、うつ状態に陥ることもあるという恐ろしい病気です。聞き慣れない病名ですが、現在、この病に悩まされている人は8人に1人。国内だけで、実に1500万人近い数に達します。それも、20代から50代のストレスを受けやすい女性が、最も多いというのです。
でも、なぜI・Kさんは、この病にかかってしまったのでしょうか?私たちは、ストレスを感じると、無意識のうちに、ある行為をします。それが、「上下の歯の噛みしめ」。I・Kさんの場合も、そうでした。再就職・家事と仕事の両立など、急激な環境の変化によって強いストレスがかかり、無意識に歯を噛みしめることが増えていたのです。そして、その時、彼女の体内では、あることが起きていました。
歯を噛みしめると、舌は上アゴに押し当てられます。すると、唾液がのどの奥にたまり、体が反射的にたまった唾液を飲み、空気も一緒に飲み込んでしまうのです。実はこれこそ、この病を引き起こす最大の原因。ストレスのため、頻繁に歯を噛みしめていたI・Kさんは、そのたび胃に少しずつ空気を送り込んでいたのです。やがて、彼女の胃は送り込まれた空気で膨らみ出し、いつしか正常な時のなんと3倍近い大きさにまでなっていました。
それがあの「ゲップ」や「お腹の張り」、「食欲不振」を引き起こしていたのです。「胸の痛み」も、大きく膨らんだ胃が心臓を圧迫したため感じたこと。心臓そのものには、全く異常がなかったのです。この病の最大の落とし穴は、痛む場所を調べてもなんら異常がないため、医師が痛みの原因を見つけにくいこと。そしてこのことが、患者のストレスをつのらせてしまいます。その結果、病状はますます悪化、最悪の事態に陥ってしまうのです。幸いI・Kさんは、専門医による適切な治療を受け、順調に回復。今では体の異変はすっかり治まり、元気に毎日を過ごせるようになりました。
「噛みしめ呑気症候群にならないためには?」
(1)予防器具として、医師の診断により患者ごとに作られるマウスピースがあります。
(2)このマウスピースを口にはめることで、自分の噛みしめ具合を実感することができるため、
噛みしめる回数をかなり減らすことが出来るのです。
(3)もし、気になる症状があれば、迷わず、心療内科などの専門医を受診することをおすすめします。
参考 たけしの本当は怖い家庭の医学
|
BACK
|